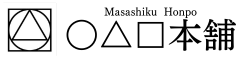神と人間 安心立命への道しるべ
ー 五井 昌久著
第二章 神と人間との関係
人間とはいったい、いかなる者であろうか。
この問にたいして、はっきりかくかくの者であると答え得る人ははなはだ稀なのではあるまいか。一見なんとなく考えすごしてしまうこの問が、人間世界の幸福を創りだす最も根抵になる問題であり、最もむずかしい答なのである。人間とはいかなる者か、我とはいったい何か、これがわかった時、その人は永遠に救われ、多くの人間がこの問に答え得る時、人類は救われ、地上天国の実現が見られるものである。
今迄に幾多の哲人、宗教家がこの問題に立ち向かい、あるいは百パーセントその問題を解明し得て覚者となり、あるいは半ば知り得て学者となり、あるいは誤り解してみずからの肉体生命を断ち、あるいは唯物思想家、唯物行動家となって、世界をますます混乱せしめた。かくて人間の本性を識り得た人が時代別にすると僅少であったため、現代にいたるまで人類は混迷をつづけてきたのである。
私はここで、ひとまず、私の信ずる、救われに入る人間観を、簡単に述べて、しだいに本題に入ってゆきたい。
人間は肉体のみにあらず、肉体のうちに、生命となって活動している何かがある、と認識して、そうした方向に生きている人。それは天国への階段を一歩踏み出した人である。
人間は霊が主であり、肉体が従である、という思いに入った人。これは同じ階段を二歩三歩昇った人びとである。
人間は神によって創られた者であって、あくまで神の下僕(しもべ)である、と、ことごとに神の審判(さばき)を恐れつつ、しかし行いを謹しんで神にすがっている人びと。この人びとは、真の人間観からいまだ遠いが、他人を傷つけぬ場合は、天国の階段を昇り得る。
人間は神によって創られた被造者であるが、神は愛であるから、愛の行いを積極的にしていれば、決して自己に不幸はこないのである、と確信している人。この人も天国の階段を昇っている。
神のことも、霊のことも、特別に考えぬが、ただ、ひたすら、素直な明るい気持ちで、愛他行をしている人。この人も天国に昇り得る。
肉体界以外のことは知らないが、素直な明るい気持ちで、愛他行ができ、しかも、神仏の存在を信じ、あわせて、この地上世界が必ず善くなることを信じて生活している人。この人は天国の住者である。
人間は霊であり、肉体はその一つの現れであって、人間そのものではない。人間とは神の生命の法則を、自由に操って、この現象の世界に、形の上の創造を成し遂げてゆくものである、と識って、それを実行している人。
この人は覚者であって、自由自在心である。即ち、個の肉体を持ちながら、みずからが、霊そのものであることを自覚し、その霊とは神そのものの生命であることを識り、神我一体観、自他一体観を行動として表現してゆく人、例えば、仏陀、キリストの如き人びとである。
真の人間を知るということは、神を知るということと一つである。いかに神、神と神を追い廻しても、その人の行いが愛と真心にかけていては、その人は真の人間をしらぬのであるから、救われるわけがない。
人間の尊いのは肉体が偉大だからでもなく、肉体の知識が秀れているからでもない。肉体の知識が多いのはよいが、あくまで、それも人間の本性、霊的智慧、いわゆる神智を元にしていなければ、かえって人類を不幸に陥れる。唯物論者の行動が非常に理論的に巧緻でありながら、それを行動にうつすと、社会を不穏にし、世界状勢を不安動揺せしめてゆくのは、神智によらないからである。即ち人間はいったいいかなる者かを知らないからである。
昔の私がそうであったように、世界の人びとの大半が、人間とは肉体そのものであり、精神とは肉体の中に存在する、ある機能の働きである、と思っている。
人間とは五十年、六十年、この社会に生存していて、後は灰になり無になってしまうものと思っている。死んでしまえばそれまでのもの、と思いこんでいる。
はたして人間は肉体の滅亡をもって、最後の終止符になるであろうか。私は即座に、否と答える。
なんとなく偶然にこの世に生まれ出て、食べたり飲んだりして肉体を維持し、ただなんとなく、社会生活を営んで、妻をめとり、夫に嫁し、子を生み育て、そして死んでゆく。人類の大半はこのような生活を繰り返して、今日にいたっているのであるが、それでは済まない、何か漠然とした不安の想いが、その大小にかかわらず、人びとの胸の中に去来しているのではなかろうか。このような生き方ではあまりにも無意義であり、無目的でありすぎる。このような生き方の他に、何かある。何があるかわからない。わからないが、またわかろうと積極的に思わない。こうした想いが一般人の心であって、その中の少数の人たちが、そのままで済まされずに、社会改革に乗り出し、思想活動に加わり、また一方の少数人は自分自身の心の内面に立ち入って、深く突きつめ、神を知り、霊を知るにいたる。ともに現況における心の苦しみを突き破ろうとしての動きなのである。
大衆は流れているのである。時間の動きとともに、人類業生の烈しい渦の中を右に左に流されてゆくのである。
その場、その時々の喜怒哀楽、渦をつかんでいったい何になろう。それが、こよなき歓喜のように見えたとしても、渦は、はかなく消えてゆくものである。
形あるもの、それは形なきものの影である。形あるものが、形あるそのままで見えるようでは、その人は救われない。形あるものの形のみを変えて、社会改革を実現したとしても人類は救われない。形、型、組織、制度、と形の世界、物の世界のみに固着した眼をもった思想は人類を滅ぼしこそすれ、救うことにはなり得ない。
人間とは肉体だけではないのである。神、すなわち宇宙に遍満せる生命が、その創造せんとする力が、個々の人格に分けられたもので、しかも横においてつながり合い、協力し合って、その与えられた力を、縦横に、自由無礙に発揮し、形ある世界に、完全なる神の姿を画き出そうとしている者である。
神とは宇宙に遍満する生命の原理、創造の原理であり、人間とは神の生命を形ある世界に活動せしめんとする神の子なのである。
このような、神と人間との関係を知り得たならば、この現象世界のいかなる変動の中にあっても、動揺せぬ生き方ができるようになるのである。
そこで各章にわたって、でき得るかぎり詳しくこの関係を書き綴るつもりである。
God and Man ~Guideposts for Spiritual Peace and Awakening
ー Written by Masahisa Goi
Chapter 2: The Relationship between God and Human Beings
What is a human being?
In answer to this question, I would expect to find extremely few people who can clearly state what the human existence is. This question, which passes through people’s minds without ever really capturing their attention, is the most fundamental one for creating happiness in the human world, and it is also the most difficult question to answer. When a person understands what sort of existence a human being is, and what exactly the ‘self’ is, that person has been liberated forever. When many people are able to answer the question, humankind will have been delivered of its suffering and heaven will be realized on earth.
Up to now, many philosophers and people of religion have confronted this issue. Those who were able to resolve it fully became awakened ones. Those who were able to understand it partially became scholars. Others, who understood it incorrectly, terminated their own lives or else became materialistic thinkers or activists who served to further confuse the world. And since those who could understand the real nature of human beings have been few within each era, humanity has remained confused up to the present.
At this point, before proceeding to the main subject, I would like to briefly describe the views on human nature which, I believe, lead to human deliverance.
People who recognize that a human being is not merely a physical body, but that within the physical body there is something—known as life—which is actively working, and who live according to this understanding: these people have taken one step on the stairway to heaven.
People who have reached the thought that spirit is master in a human being while the physical body is subordinate: these people have climbed the same stairway two or three steps.
People who believe that human beings are created by God and are God’s servants and nothing else, and who fear God’s judgment in everything, but are cautious in their deeds and cling to God: these people are still far from a true understanding of human beings; however, if they do not hurt others, they are able to climb the stairway to heaven.
People who think that human beings are creatures made by God, but that since God is love, if they positively keep acting in the spirit of love, unhappiness will never visit them: these people are also climbing the stairway to heaven.
People who do not particularly think of God or spirit but just sincerely perform actions of love with a bright and straightforward attitude: they also are able to climb to heaven.
People who, though they know nothing aside from the physical world, can spontaneously perform actions of love with bright feelings, believe in the existence of God, and live with the conviction that this world will surely improve: these people are already living in heaven.
People who know that man is a being who accomplishes the creation of that which has shape in this phenomenal world by freely utilizing the divine law of life, with the realization that a human being is spirit, and that the physical body is one of a human being’s embodiments and is not the true human being itself, and who put this understanding into practice: these people are awakened ones. Their minds are completely free from limitation. While having a physical body, they realize that they are, in truth, spirit. Knowing that spirit is divine life itself, they express their sense of oneness with God and others through their actions. Two examples of this would be holy people such as Gautama and Jesus Christ.
Knowing the true human being is the same as knowing God. No matter how hard one may seek God, if one’s actions are lacking in love and sincerity, one does not know the reality of a human being and cannot find true peace of mind.
The preciousness of a human being does not depend on the greatness of the physical body, or on the excellence of one’s knowledge. It is good to have a lot of knowledge, but if this knowledge is not rooted in the true nature of human beings, or spiritual wisdom (divine wisdom), it will, rather, entrap humankind into misfortune. Though the theories of the materialists are very elaborate, when they are put into action they create a restless society and disturb the world situation. This is because those theories are not based on divine wisdom. In other words, the materialists are not aware of what a human being really is.
As I did in the past, the majority of people in this world think that a human being is a physical body, and that the mind is a function existing within the physical body. They believe that a person lives in this society for some fifty or sixty years and then is reduced to ashes and disappears into nothingness. They are convinced that with death everything terminates.
Does the disintegration of the physical body mean the end of a human being? I promptly answer No!
Most people feel that a person is somehow born into this world by chance, maintains his or her physical body by eating and drinking, functions as a member of society, marries, raises children, then passes away and disappears into nothingness. The majority of people have lived according to this view, from birth to death and from lifetime to lifetime. Yet, not being wholly satisfied with this kind of life, do they not feel some vague and uneasy thoughts, whether large or small, recurring in their minds? This kind of life seems too meaningless and purposeless. People feel that there must be something else beyond this kind of life, but they do not know what it is. And yet, though they do not know what it is, they are not positively trying to discover what it is.
These are the feelings of the general masses. Among them, a few are unsatisfied with the way things are, and embark upon social reforms or join ideological movements. Others enter into the interior of their own minds in deep pursuit, and come to know God and spirit. Both are efforts that aim at breaking through the anguish that people are experiencing in their present lifestyle.
The masses are drifting. With the shifting of time, they are being carried right and left by the violent whirlpools of humanity’s karma.
What good does it do to grasp at the whirlpools of momentary elation and anger? Though those whirlpools may appear to hold the highest of joys, they fleetingly pass away.
That which has shape is a shadow of that which does not have shape. If one sees nothing more than the visible, tangible aspect of something, one will not be able to rise above one’s suffering. Even if social reforms are realized by changing only the shapes and forms of things, humanity will not be rescued from its anguish. Thoughts which adhere only to the world of material substances, or the world of forms or shapes, models, organizations and systems, are what ruin mankind—they certainly cannot save it.
Human beings are not of the physical body alone. God, the life that prevails throughout the universe, divided out its creative power into individual personalities; and those individual personalities are human beings, who strive to draw the perfect image of God within the world of shape by interrelating and cooperating with each other on the horizontal plane as they fully and freely command their given powers in all directions.
God is the principle of life and the principle of creation prevailing throughout the universe. Human beings are the children of God who are trying to activate God’s life in the world of shapes and forms.
If you are able to understand this relationship between God and man, you will be able to live unperturbed by any fluctuations in this phenomenal world. Now I would like to write about this relationship in as much detail as possible in the following chapters.
Dios y el Ser Humano (Spanish Edition)
Deus e o Homem (Portuguese Edition)